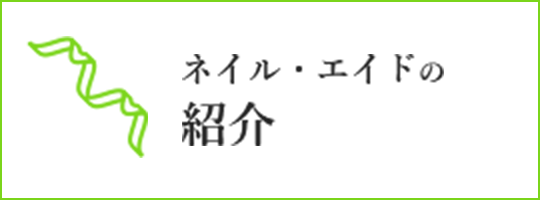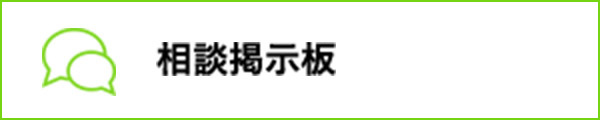「外反母趾になってしまったけれど、どうやって治せばいいの?」「病院ではどういった治療を受けるんだろう」と疑問に思われている方もいるのではないでしょうか。外反母趾になったら、病院で保存療法や手術療法などの適切な治療を受ける必要があります。
そこで今回は、外反母趾の治し方についてご紹介します。病院での治療法だけでなく、予防にも役立つセルフケアについてもご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
この記事の監修をお願いしている簗医師の、解説記事へのリンクを文中に掲載しています。より詳しく知りたい方は、簗医師の解説記事もご覧ください。不明な点は掲示板(https://medical-media.jp/bbs/)からご相談ください。
外反母趾の方は、巻き爪や陥入爪に悩まされている方も多くいます。
一般的に「陥入爪」と「巻き爪」という言葉は混同して使われている場合がありますが「陥入爪」と「巻き爪」は別の状態を表します。
この記事ではわかりやすいように一部「巻き爪」を含めて「陥入爪」という言葉で表現している場合があります。違いについての詳細は解説記事を参照してください。
- 陥入爪=爪甲が側爪郭に陥入し炎症を引き起こした状態
- 巻き爪=爪甲が彎曲した状態
簗医師の解説記事:https://medical-media.jp/basic/#s5
外反母趾の原因とは

外反母趾とは、足の親指の先が内側に曲がり、指の根元部分が外側に突出した状態のことです。外反母趾になる原因には、以下のようなものがあります。
- 靴による圧迫
- 筋力低下
- 肥満
- 誤った歩き方
- 扁平足の影響
- スポーツの影響
- 生まれつきの指の形
なお外反母趾の原因については、以下の記事でも詳しくご紹介しています。こちらもぜひ参考にしてみてください。
外反母趾の治し方【病院での治療編】
外反母趾の治療を病院で受ける場合、症状に合わせてさまざまな治療法が選択されます。ここからは、外反母趾に対する病院での治療法についてご紹介します。
保存療法

外反母趾の症状が軽い場合は、保存療法が行われます。保存療法の種類は、主に以下の通りです。
- 靴指導
- 運動療法
- 装具療法
- テーピング療法
- 骨格矯正
- 薬物療法
ここからは、それぞれについてご紹介します。
靴指導
外反母趾になる主な原因は、靴による足指への圧迫です。変形の進行や痛みを抑えるために、正しい靴の選び方に関する指導が行われます。場合によっては、医師の指導のもとでインソールの使用が推奨されることもあります。
運動療法
軽度~中程度の外反母趾の進行を食い止めるため、運動療法が選択される場合もあります。運動療法では、足の指でグーとパーを作る体操が採用されることが多いです。この体操をすれば、母趾外転筋と呼ばれる筋肉を鍛える効果が期待できます。
装具療法
靴指導と運動療法に加え、痛みがある場合は装具療法も実施されます。装具の種類はさまざまですが、足底挿板やトースプレッダーなどが用いられることが多いです。足底挿板は、使う方の足に合わせて作る中敷きタイプのアイテムを指します。トースプレッダーは、人差し指と親指の間に挟んで親指を開く装具です。
足専門のクリニックで治療を行っている桑原医師が監修し、国内メーカーのタビオが製造している「外反母趾サポートソックス」は外反母趾サポーターとして、おすすめです。
外反母趾サポートソックス:https://item.rakuten.co.jp/himawari-corp/tabio2224/
テーピング療法
足の変形を改善し、正常な状態を身体に定着させるために、テーピング療法が用いられることもあります。外反母趾用のテーピングで固定することで、良い状態を身体に記憶させます。
骨格矯正
歩くときなどに足が正しい位置に接地できるよう、骨格矯正の施術が行われるケースもあります。足回りだけでなく、身体全体の筋肉も調整することで、骨格の歪みが再発するのを防止し、外反母趾を根本から改善していきます。
薬物療法
痛みの程度によっては、薬物療法が併用されることもあります。湿布やクリーム、軟膏などの消炎鎮痛剤入り外用薬を他の治療法と組み合わせることで、痛みを和らげる効果が期待できます。
手術療法

外反母趾の症状が進み、保存療法では痛みが抑えきれない場合は、手術療法が行われます。手術にはさまざまなタイプがあり、変形の程度や足の形、体型、年齢などの状況を考慮して選択されます。
足のトラブルを適切に診察してくれる医療機関を探すのは難しいと感じています。以下の記事は巻き爪の医療機関の探したかについて解説した記事ですが、参考になる部分も多いと思います。
簗医師の解説記事:https://medical-media.jp/column/when-it-becomes-an-ingrown-nail/
外反母趾の治し方【セルフケア編】
外反母趾が軽度の場合は、自宅でのセルフケアを行うのもおすすめです。ここからは、予防にも役立つ外反母趾のセルフケアについてご紹介します。
足に合った靴を履く

外反母趾を防ぐためには、足に合った靴を履くのが大切です。つま先部分がゆったりとしていて、かかとや甲が靴紐などでしっかり固定できる靴を選びましょう。先の尖った靴やヒールは、足先に負担がかかるので避けるのが無難です。
正しい歩き方をする
正しい歩き方は、着地の際の重心を意識してみましょう。かかと、指の付け根、指の3点に重心を置くのが正しい歩き方です。3点歩行では重心が安定するので、親指や側面に過度な圧力がかからず、変形を防止できます。
一方でかかとと足の付け根のみで着地する2点歩行は、身体のバランスが崩れて外反母趾につながりやすいので注意しましょう。
足の骨格のアーチが崩れることが、外反母趾の大きな要因です。アーチが崩れる原因はいろいろありますが、持って生まれて遺伝的な要素も大きいです。アーチが崩れることで引き起こされる様々な症状が出てくる前に、インソールによるアーチをサポートや、適切な靴の選択など、フットウェアの調整が重要になります。
手術以外の方法は、厳密にいうと、治すというよりは進行を予防する治療法と感じています。異変を感じたら、早めにアーチをサポートするインソールを使用することをお勧めします。
以下の記事では、自分の足に合った靴の選び方や正しい歩き方について、画像付きで詳しく解説しています。
簗医師の解説記事:https://medical-media.jp/selfcare/#s2
つま先運動を行う
足のアーチ崩れを防ぐために、つま先運動を行うのもおすすめです。つま先運動をすると足裏の筋肉が鍛えられ、足裏のアーチをきれいに保つ効果が期待できます。つま先運動は、以下の手順で行いましょう。
- 足を肩幅に開く
- 息を吐きながらゆっくりかかとを上げる
- 息を吸いながらゆっくりかかとを下げる
上記の動きを、10回×2セットを目安に行います。慣れてきたら、少しずつ回数を増やしていきましょう。
足のマッサージを行う
外反母趾予防のために、足のマッサージを行うのもおすすめです。マッサージを行うことで血液やリンパの流れを良くし、むくみ防止や疲労回復の効果が期待できます。凝り固まった足裏の筋肉をほぐすことにより、歩くときに筋肉を正常に使えるようにするのが大切です。
足のマッサージは、以下の手順で行いましょう。
- 足にオイルなどをなじませる
- 足を3ヶ所(内側、中央、外側)にわけて親指の腹でマッサージする
両手の親指を重ねれば、しっかりと力を込められます。入浴中やお風呂上がりなど、リラックスしながら行いましょう。
扁平足の場合、インソールを使用する

扁平足の場合、足のアーチをサポートするためにインソールを活用するのがおすすめです。市販のインソールが足に合わない場合は、医療用のオーダーメイドインソールを使うのが良いでしょう。インソールによって足の負担を軽減し、症状を和らげる効果が期待できます。
運動を習慣にして、筋肉を鍛える
足の柔軟性や筋力を向上させるためには、適度な運動を習慣にするのもおすすめです。足の筋力低下を防ぎ、正しい姿勢と足の形状を保ちましょう。
まとめ
今回は、外反母趾の治し方についてご紹介しました。外反母趾の治療では、症状の程度に応じて保存療法や手術療法が行われます。正しい歩き方や靴の履き方などを身につけて、症状悪化を防ぎましょう。
外反母趾に伴い巻き爪になっている場合は、巻き爪矯正器具「ネイル・エイド」でケアしましょう。どちらの商品も以下のリンクから購入できるので、ぜひチェックしてみてください。
ネイル・エイドの購入はこちらから:https://medical-media.shop/
【監修 埼玉医科大学 形成外科 簗由一郎医師】
ご不明な点は、相談掲示板からご相談ください。

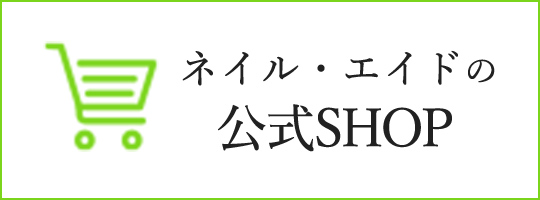
 ホーム
ホーム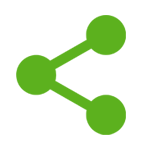 シェア
シェア 掲示板
掲示板 検索
検索

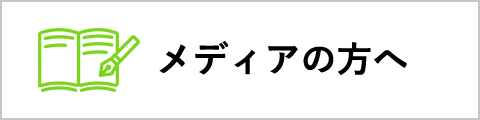



 検索
検索